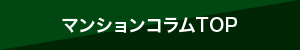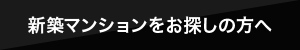簡単にできる省エネのコツ
地球温暖化や、東日本大震災に端を発した電力不足…省エネは今や誰もが向き合うべき課題です。
いきなり省エネの為に、ライフスタイルの大転換!というのは難しいですよね。しかし一人一人の少しの心遣いが、やがて大きな輪となって省エネの効果につながります。今回は日々の暮らしの中で無理なく取り入れられそうな、省エネのヒントをご紹介します。
限りあるエネルギーを大切に使うため、“時”と“場所”を考えた省エネを。
1979年に省エネ法が制定されてから30余年。日本の省エネ技術は進んだものの、生活スタイルの変化により家庭でのエネルギー消費量も増加し続けてきました。環境配慮型の省エネとは別に、震災後は電力不足による停電を防ぐため電力需要の高い時間帯での“ピークカット節電”が呼びかけられています。今、限りあるエネルギーを効率的に使うために、“時”と“場所”に配慮することが求められています。将来のための恒常的なエネルギー消費を抑える工夫はもちろんですが、むやみに“節電!” “省エネ!”と構えるのではなく、“締めるところは締める”ことから始めてみてはいかがでしょうか?
-
家庭における究極の省エネ行為とは?
家庭における消費電力は、エアコン、冷蔵庫、照明器具、テレビ、の順に高くこの4つだけで、約7割の電気が使われています。
特にエアコンが占める割合は高く対策は不可欠です。フィルターのこまめな掃除やカーテンを断熱性に優れたものに交換することで効果的に空調設備を使用できます。また、人は羽織る物で体感温度を調節し、外出する際や就寝前は早めに消しましょう。 年中無休の冷蔵庫は、季節の変わり目に応じて設定温度を変えましょう。また、ドアの開閉を減らし、詰め込みすぎず7割程度の備蓄にすることで冷却効率を保つことができます。
照明器具やテレビは、こまめなスイッチオフが基本です。また、テレビやPC等の待機電力カットには“スイッチ付タップ”が便利です。 いずれも定番ワザですが効果は確実です。全部は無理でも、いくつか実践するだけで省エネ効果だけでなく、光熱費カットにもなるので、取り入れてみる価値は大きいです。
また、“家を留守にすること”は家庭における究極の省エネ。特に電力需要の高まるコアタイム(13時~15時)に外出し、図書館やデパートなど人の集まる場所に行くこと自体がピークカット節電に貢献することになります。 
-
家事の省エネ化。ポイントは“まとめ家事”
省エネは節電だけでなく、炊事・洗濯・掃除といった家事においても出来ることがあります。
炊事の際にエネルギー消費量が多いのは、ガスコンロと給湯器。ガスの調理に、電子レンジを組み合わせましょう。
根菜類の下ゆでや、フライパンで焼き目をつけた後の加熱に電子レンジを使えば、ガス代の節約に加え時間短縮にもなります。洗い物は食器の汚れをあらかじめヘラやボロ布で拭いておいたり、水に浸けておけば汚れ落ちが良くなります。また、お湯を流しっぱなしではなく、貯め洗いを心がけて。ちなみに給湯器はエネルギー効率が高いので、お湯を沸かす時は水からではなく、給湯器のお湯を使うと効率的です。
洗濯は少量を毎日するのではなく、洗濯機の容量に合わせて出来るだけまとめ洗いをして洗濯回数を減らしましょう。
掃除での省エネはやはり掃除機。カーペットなどの掃除機でないと取りきれない場所以外は、ホウキとちり取り、雑巾でキレイになるものです。省エネになるだけでなく、消費するのは自分のカロリーかと思えば、まさに一石二鳥です。
ピークカット節電の観点では、人によってライフスタイルが異なるので一概には言えませんが、可能なら影響の少ない土日に家事をまとめてするのがベターと言えます。 
-
住まいと省エネ
近年は住まいにおける省エネ技術も進化しており、冷暖房や給湯、照明などの設備でも省エネ仕様が積極的に取り入れられています。
冷暖房の面では、“複層ガラス”。2枚のガラスの間に中空層を設けることで断熱効果を発揮し、空調の冷暖房効率を高めます。 給湯器は、消費エネルギーが大きいだけに設備の性能による省エネ効果の差が大きいもの。“エコジョーズ”や“エコキュート”といった従来より熱効率が高く、ランニングコストが抑えられたものの普及が進んでいます。
照明では、LED照明が話題になっており、ご存知の方も多いのではないでしょうか。白熱電球に比べて消費電力が少なく寿命が長いので、廊下のダウンライトなど取替えにくい場所などに便利です。今後さらなる性能の進化や、低価格化も期待されています。
省エネは無理なく続けられる事が肝心。ハード面での進化と私たちが出来ることをうまく組み合わせていきたいですね。